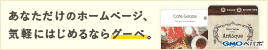BGM
週明けの本日は「BGM」について
クライアント様からたまに聞かれる「オフィス内のBGM(オフィスBGMといわれています」
ひと昔では考えられなかったことですが、個人的には昔から推奨しております。
業務をさまたげないジャンルや音量調整が必要ですが、効率向上、創作性の向上等の効果があると言われています。
そのため導入する企業様が増えており、オフィス、休憩場、などの場所によって違う曲調やジャンルのものを流したり、時間帯や作業によってテンポの違う曲を流しているところもあります。
基本的に、インストゥルメンタルで小さい音量で流されており、歌が入ってしまうと気が削がれてしまう場合があるため歌入りの曲は避けられています。
※ 当社ではJAZZを流しておりましたが、JAZZが苦手なスタッフ(眠たくなるそうです)がいるため今は曲無しでいます。
ひとつ注意点
あまり気にされていない方々が多く、後に問題になる場合もあることがあります。
たまに耳にする「著作権」。
ざっくりいうと、曲には利用に関する法律がありまり、その法律で作った人、歌っている人の権利が守られており、その権利が著作権になります。
社員のみを対象にするような場所では問題ないと思いますが、店舗として利用していたり、多くの来客がある場合は、日本音楽著作権協会(JASRAC)に届け出しなくてはいけません(利用料金が発生し、広さや利用人数によって金額が変わります)
また、無料で使用可能とされていても、すべての作品には著作権が存在します。
保護期間が過ぎたものや作者が著作権を放棄したものでない限り、オフィスで無断使用すると著作権違反となるおそれがあります。
著作権フリーの曲を使用したり、テレビやラジオの放送を流したりする場合、手続きは不要です。
利用方法に問題がないか、BGMを導入する前に、社内でチェックしておくことをおすすめします。
「いろいろめんどくさい!」
と思われる場合、BGMについて古くから携わっているUSEN様にご相談されると良いかもしれません。
※ USEN様を推奨していることではありません。
リラックスしながらお仕事ができる環境作りも大切な「業務」だと思っています。
企業主様、事業主様、福利厚生のひとつとして考慮するのもアリだと思います。
熱中症
少し間があいてしまいました・・・
本日は「熱中症」のお話し
前回キッチンカーの調理スタッフの健康管理について少し書きました。
そのさい記載した「熱中症」ですが、私も軽度のものに掛かり、娘が倒れるまでになりました。
私はただの不摂生だと思うのでとりあえずは放置ですが、娘の場合は酷かったので病院に行き診察いただきました。
診察結果などをうかがったところ、アレルギーで鼻腔が詰まり炎症。
排出されていない菌がリンパに入りリンパも炎症。
鼻腔炎で呼吸整わず、リンパの流れが悪くなり発汗がうまくいかず、体内の熱がこもり熱中症になったそうです。
また、熱中症予防のためタブレットをなめさせていたのですが、どうやら食生活から考慮すると塩分の過剰摂取になってたのでは?とのこと。
(※ タブレットがダメと言っているわけではありません)
塩分の過剰摂取で血がドロドロになり血流が弱くなるため体温調整が利きが悪くなる場合があるそうで、先程の炎症と重なると熱中症の症状が悪化する場合が多いそうです。
「暑い」からだけではないのはわかっていましたが、塩分の過剰摂取も要因になるとは思いませんでした。
今回の場合、テストの勉強中お菓子をたくさん食べ、勉強+呼吸が整っていないからの睡眠不足がポイントのようです。
イベントや勤務中にたくさん汗をかいている場合や運動を行う場合は大丈夫だと思いますが、現在の体調、飲み物、食べ物にご注意いただき熱中症対策を行ってください。
ちなみに、スポーツドリンクも大量に飲む場合は「過剰」になってしまうので「薄めて」飲んがほうが良いそうです。
猛暑の梅雨
本日は「キッチンカー」のお話し
梅雨だというのに雨がが少なく(突然のスコールが発生しておりますが)暑い日が続いております。
先日では最高気温が36℃と発表され、車の社外温度は40℃、アスファルト上では46℃と異常な状態でした。
そんな中でもイベントはあります。
キッチンカーも多く出ており、大変にぎわっていると耳にします。
そんな中、お客様、飲食スタッフ共に懸念される「熱中症」。
私も数回経験しておりますが、かなりしんどく命の危険が伴います。
お客様のケアが第一に考えられていますが、実は、キッチンカーのスタッフの方が危険だったりします。
最近制作されたキッチンカーは冷暖房完備だったりするので幾分かマシですが、装備の無い旧型は大変危険です。
スポットクーラーや、冷却シートを体に付けるなど対策をしている方が多くいらっしゃいますが、真夏では調理場の温度は50℃近くなる事もあり間に合っていません。
そんな事情を知ってか知らずが、水分補給をしていると待っているお客様が「不衛生」「ズルい」などと心無いお言葉をいただいたりします。
素手で汗をぬぐい、その手で飲料し、そのまま調理するなら言われるのは当然だと思いますが、手袋をし、飲料後はアルコールで消毒し、調理に取り掛かっているので「不衛生」ではありません。
本音を言うならば、灼熱の中でゴム手袋をすると余計暑くなり汗がたまるほどかいているので「素手の方が衛生的」だと思ったりするのですが・・・
ひと昔では、素手で調理、キッチンカーも暑ければドアを開口して行っておりました。
現在では保健衛生上不可であり、保健所の指導でも許される行為ではありません。
商売とはいえ、現実とルール、食の安全と自身の保身、その狭間で暑さの中働いていらっしゃる方々に心無い言葉を投げかけるのは止めていただければと強く思っています。
キッチンカースタッフの方々、お体にお気を付けて。
視覚発達支援センター
今日は「クライアント様」のお話し
昨年から「発達障害」の子どもたちに関わることが増えてきました。
先日のラジオ出演でもご一緒させていただいた「名古屋敬進高等学院」様から始まり、イベントやセミナーにも携わりました。
今回は全く違うご縁から、「視覚発達支援センター」様のWebサイト(ホームページ)を制作させていただきました。
視覚発達支援センター https://nagoya-keishin.jp/
視覚発達支援センターでは、視覚認知にトラブルを抱えている子供たちを対象に、主訴や検査結果の評価をもとに、ビジョントレーニング、作業療法、言語療法、学習支援を行っています。
学習支援も状況に応じてオンラインでも実施されており、保護者を対象にしたペアレントトレーニングにも対応しており、とても好評を受けています。
場所は千葉県浦安市にあるので、愛知県からでは遠くあまり利用者がいないのでは?と思ったのですが、なんと全国から要望があり、遠方からも通われている方がいらっしゃるそうです。
もし周りにで視覚認知に不安があるような子どもがいらっしゃるようでしたら、一度ご予約を取っていただき診断を受けると良いのでは?と思います。
どんなことをするかなどがWebサイトに記載されておりますので、ぜひ一度ご覧ください!
ラジオ出演!
本日は「お知らせ」です。
昨日、MID FM761様(https://midfm761.com/)のラジオ番組「魁TOPインタビュー」にゲスト出演させていただきました!
パーソナリティーは書道家の一ノ瀬 芳翠先生(https://www.facebook.com/housui.ichinose)で、メインゲストの「名古屋敬進高等学院の中田学院長」のお供で参加させていただきました。
「名古屋敬進高等学校」 https://nagoya-keishin.jp/
名古屋市天白区にあり、福岡県が本校舎の「明蓬館高等学校」のサポート校です。
私立の全国広域制通信性高等学校で、発達や学校生活に課題を持つ方に特化し、特別支援付の普通科高校教育をしている通信制の学校です。
「サポート校」
高等学校通信教育を受けている生徒に対して、学習に対する支援を行う教育施設の事です。
実は、名古屋敬進高等学校の立上げに当社が携わっており、コンサルティングさせていただきました。
最近ではセミナーを開催させていただいたりしております。
ご縁で付き添うをさせていただくことになったのですが、なぜがサブゲストとして出演することになり、恥ずかしながらたどたどしくお話しさせていただきました。
オンエアではバッサリ切られているかもしれませんが、愛知県の方々、ぜひお聞きください!
一ノ瀬先生様、堀口様、ありがとうございました!